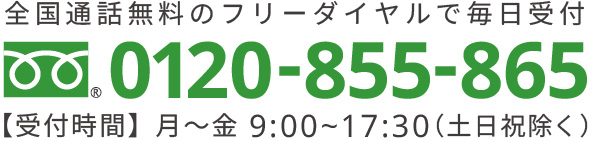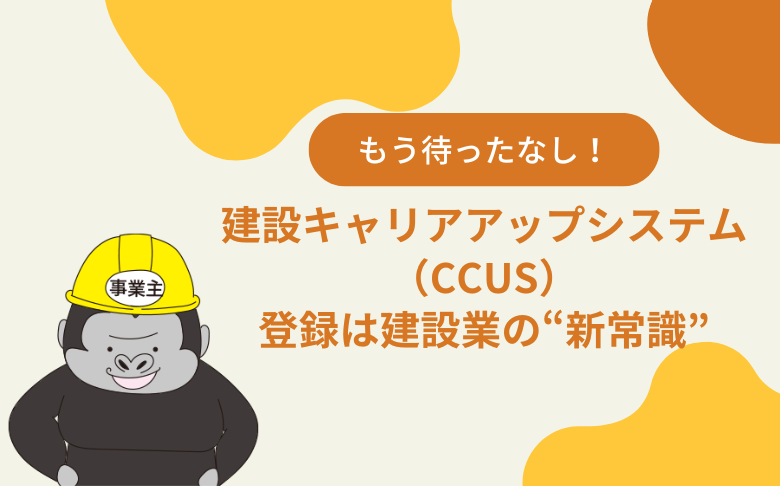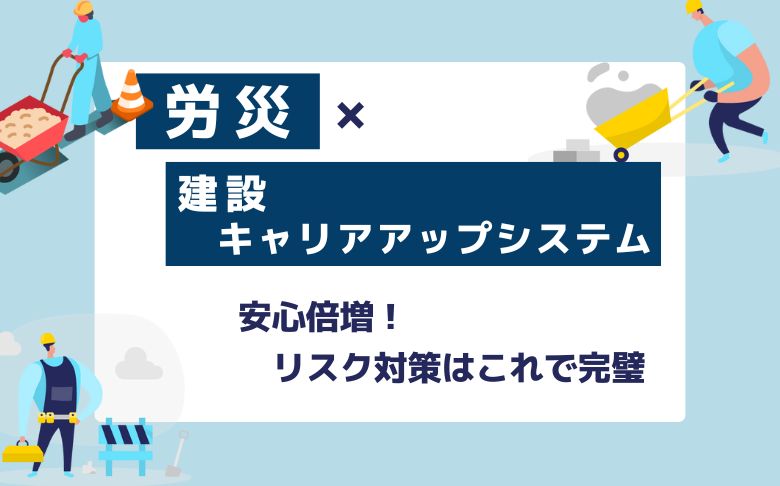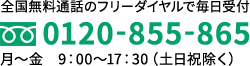公開日:2025年9月30日

この記事はこんな人にオススメ
- 一人親方と中小事業主の労災保険の違いがいまいちわからない社従業員を雇い始めた(または雇う予定の)建設業の社長
- 「一人親方の労災保険」と「中小事業主の労災保険」の違いがよくわからない社長んいる方
- 取引先に安心してもらうために取引先からの信用度を上げたいと考えている社長
はじめに
いつもお仕事お疲れ様です。
「労災保険」と聞くと、なんだか複雑で難しそう…そう感じていませんか?
特に建設業では、「一人親方の労災保険」と「中小事業主の労災保険」があって、その違いがわかりにくいですよね。
この記事では、従業員を雇っている(またはこれから雇う)建設業の中小事業主である社長に向けて、一人親方の労災保険と、社長が入るべき中小事業主の労災保険の違いを、わかりやすくご説明します。
「一人親方の労災保険」と「中小事業主の労災保険」の決定的な違い
「一人親方の労災保険」と「中小事業主の労災保険」は、同じ「労災保険の特別加入制度」ですが、入る目的と加入できる条件が全く違います。
一人親方労災保険:赤の従業員を雇っていない社長や職人が加入できる労災保険
中小事業主の労災保険:従業員を雇っている社長が、自分自身も守るために加入できる労災保険
もし社長が従業員を雇っているのに、ご自身は「一人親方」として労災保険に入っていたとしたら実は、それは少し注意が必要です。
従業員を雇うと、その会社は「事業主」と見なされ、社長ご自身は「一人親方」としては扱われなくなってしまいます。
社長が労災保険に「特別加入」する必要性
「従業員の労災保険に入っているから、社長は大丈夫だろう」と思っていませんか?
実は、労働基準法上の「労働者」にあたらない社長様、会社の従業員と同じ労災保険では守られません。
だからこそ、万が一、社長が現場で怪我や病気をされてしまった時のために、「中小事業主の労災保険」に特別加入しておくことが大切です。
社長ご自身を守り、安心して仕事に打ち込むためのお守りのようなものですね。
特別加入はなぜ取引先からの信用につながるのか
ここが、社長の事業にとって非常に重要なポイントです!
建設業界では、元請けや取引先が、下請け業者を選ぶ際に、「しっかりとした体制で仕事をしているか」を厳しくチェックします。
そのチェック項目の一つが、「社長が労災保険に特別加入しているか」、つまり「会社全体でリスク管理を徹底しているか」という点です。
もし社長が特別加入をされていない場合
- 「社長が万が一の時に無防備な会社だ」
- 「法律に基づいた正しい手続きをしていないかもしれない」
と、取引先に不安や不信感を与えてしまう可能性があります。
安心できる会社と思ってもらうために
中小事業主の労災保険に特別加入をしているかどうかは、会社が「従業員はもちろん、社長自身も守る体制を整えている」という証明になります。
これは、
- 「法律をしっかり守っているコンプライアンス意識の高い会社だ」
- 「リスク管理ができていて、安心して仕事を任せられる」
というメッセージを、取引先に伝えることと同じです。
つまり、「中小事業主の労災保険」に特別加入することは、単に保険に入るだけでなく、取引先からの信用度を上げるための重要な営業ツールにもなるのです!
「特別加入をしているかどうかで取引先からの信用度が違う!」
これは建設業界では常識となりつつあります。
まとめ
建設業の中小事業主である社長が、一人親方の労災保険ではなく中小事業主の労災保険を特別加入することは、ご自身を守ることはもちろん、取引先からの信用を得て、安心できる会社と思ってもらうために欠かせません。
国が定める正式な労災保険の特別加入制度を正しく理解することで、安心して仕事ができ、取引先からの信用にも繋がります。
30年以上の安心と実績、建設業専門RJCにまずはお気軽にご相談ください!
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(労災保険)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1だから、間違いありません。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

元厚生労働省 厚生労働事務官
厚生労働大臣認可 愛知労働局長認可 建設業専門
労働保険事務組合RJC アドバイザー
林 満
はやし みつる